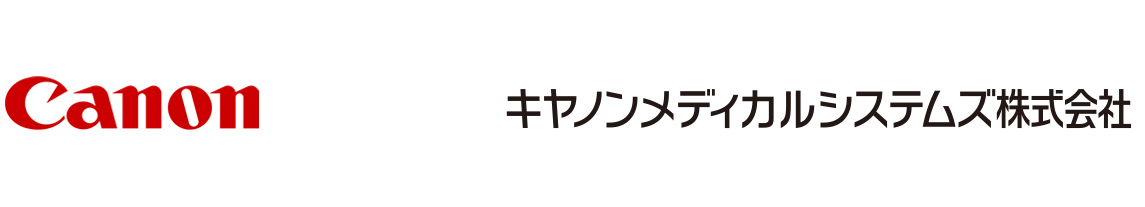特集
代替のない微細血流評価法 ~なぜ今もSMI なのか~
序説
畠 二郎(川崎医科大学 検査診断学)非造影の微細血流評価法としてのSMI(Superb Micro-vascular Imaging)が市場化されておよそ6年が経過した。見えなかったものを見えるようにしたこの技術は国際的にも高い評価を受け、SMIを用いた新知見があらゆる領域において数多く報告されるに至っていることは改めて言うまでもない。このトレンドに伴い各超音波機器メーカも微細血流表示を意識したソフトウェアを開発、市場化しているが、SMIと同等の性能を有しているとは必ずしも言えないのが現状である。当然われわれの施設でもSMIは連日頻回に使用されており、もはやSMIは新しい特殊技術というよりは、B-modeやカラードプラなどと同様に日常臨床においてルーチンに使用される手法として定着したと言えよう。つまりなぜ今もSMIなのか?という問いに対する答えは、CTやMRIも含め、その代替法が存在しないからという一言に集約される。いわゆるリキッドバイオプシーが実用化され、AIの導入が真実味を帯びているなど医療そのものが大きな変革を迎えようとしている中、今後の超音波診断機器は単にその非侵襲性や簡便性といった利点のみにその存在意義を求めていては明るい将来展望は得られず、代替法のない画像診断法としての地位を確立すべきであるというのが以前から筆者が強調していることである。SMIや超高周波プローブの開発はまさにその方向性に沿ったものであり、さらに組織分解能を持たない超音波の欠点を補う手法として組織の弾性・粘性の評価や減衰イメージングなどが実用化されているのは周知のごとくである。
ところである手法が普及し定着した場合、その適応と使用法はより洗練されるとともに、新たな適応や使用法も考案される。これはSMIも同様であり、どのような領域のどのような病態に特に有用性が高いのか、さらにどのような領域にも応用が可能なのかという議論が生ずる。またcolor-coded SMIとmonochrome SMIの使い分けや正しい解釈も今後検討されるべき課題である。今回はこのSMIの適応や有用性に関する各領域のエキスパートオピニオンを特集した。また肝臓領域においてはShear wave elastography やAttenuation imaging といった手法にも触れていただいている。鮮明な画像とともに分かりやすい解説をいただいた著者の方々に誌面をお借りしてここに厚くお礼申し上げる次第である。本特集が 多少なりとも読者諸兄のお役に立ち、ひいては医療レベルの向上につながることになれば望外の喜びである。
本ページは映像情報メディカル2020年5月号に掲載されたものです。
| 一般的名称 | 汎用超音波画像診断装置 |
| 販売名 | 超音波診断装置 Aplio i800 TUS-AI800 |
| 認証番号 | 228ABBZX00021000 |
| 一般的名称 | 汎用超音波画像診断装置 |
| 販売名 | 超音波診断装置 Aplio a450 CUS-AA450 |
| 認証番号 | 230ABBZX00018000 |
| 一般的名称 | 汎用超音波画像診断装置 |
| 販売名 | 超音波診断装置 APLIO 500 TUS-A500 |
| 認証番号 | 222ACBZX00051000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | コンベックス式電子スキャンプローブ i8CX1 PVI-475BX |
| 認証番号 | 228ABBZX00025000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ i18LX5 PLI-1205BX |
| 認証番号 | 228ABBZX00025000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ i11LX3 PLI-705BX |
| 認証番号 | 229ABBZX00035000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ i24LX8 PLI-2004BX |
| 認証番号 | 228ABBZX00026000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ PLT-1204BT |
| 認証番号 | 220AABZX00136000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ i22LH8 PLI-2002BT |
| 認証番号 | 229ABBZX00036000 |
| 一般的名称 | 手持型体外式超音波診断用プローブ |
| 販売名 | リニア式電子スキャンプローブ PLT-704SBT |
| 認証番号 | 219AABZX00218000 |